落乱ファンだけではなく、歴史が好きな人なら一度は見聞きしたことがあるはずの「いもがら縄」。
縄になるようなものが本当に食べられるの? 芋の茎の縄って強度はどうなのよ? という疑問を晴らすべく、実際に作ってみることにしました。
とは言え、本を探してもネットで検索しても詳しい作り方が分からず、結局「乾燥いもがらの作り方」および「市販いもがらの食べ方」を参考に考えた製作手順がこれ。
1:洗って皮を剥く。
2:2週間〜1ヶ月ほど天日干しにする。
3:お湯か水で戻して煮る(アク抜き)。この時はまだ味はつけない。
4:味噌で煮込んだのち、縄になう。縄状にしてから煮しめるやり方もあるらしい。
5:再度干す。2〜3週間くらい?
6:実食!
こんなアバウトでいいのかと思いつつ、いざ実験開始。
 |
 |
 |
| 長さは100cm弱、太さは最大で3cmくらい。 | 近くで見るとこんな感じ。 | 皮はナイフでスルスル剥けます。 |
生ずいき(いもがらの別名)に触るとシュウ酸カルシウムで手が痒くなるという情報があったので「ゴム手袋をするべき?」と考えながら、痒くなったらなったでネタになるからいいやー、と素手で皮剥き。特にかぶれることもなく問題ありませんでした。
肥後ずいきで検索すると要らん知識が得られます。
 |
 |
 |
| 厚剥き(上)と薄剥き(下)にしてみました。 | 上部に切込みを入れて紐を通し… | キュッと結びます。 |
 |
 |
| みょいーんと天日干し。 | そして45日後。しおしお… |
雨の日は室内干しにしたりしつつ、気候と季節も相まって2週間も干せばカラッカラのカッサカサになるかと思いきや、いつまで経っても微妙にしっとり。皮の剥き方も特に関係なく、キリがないから45日目に切り上げました。
定点観測的に毎日写真を撮っていたら100枚超えた(しかも変化が緩やか過ぎて全部並べて見比べないと分からない)ので、初日と最終日だけ載せてます。
 |
 |
 |
| 軽く洗って水に浸けます。 | 90分後。水が白茶っぽく濁ってきた。 | 2時間半後。結構プリプリに戻りました。 |
 |
 |
 |
| 蓋を開けたら ボーン! | いもがらが浸る程度のお湯に味噌300g投入。 | 煮汁が半分になったら火を止めます。 |
アクを抜くため、戻したいもがらを水から茹でます。ものすごく膨らみます。
「いもがらはエグ味がすごいから下茹で必須」「最近のはエグ味がないからアク抜き不要」と正反対な情報があったのでどういうこっちゃと思ったら、サトイモの品種によってかなり違うらしく、畑で見かけるようなのサトイモの茎は口の中がキューとなるほどシブいらしいです。ひと通り沸騰させた後にちょっと端っこを食べてみたら、エグ味はなくシャキシャキしてました。
その後、表面に線が引けるほど濃い味噌汁に絞ったいもがらを投入して気長に煮詰めます。タケヤ味噌なら良かったんだけど冷蔵庫にあったのはマルコメ。
 |
 |
| ツヤツヤプリプリが、 | しおしおひょろーん。編み目が緩んだ… |
煮汁が冷めたらいもがらを引き上げて水気を指でしごき落とし、縄にないます。
縄綯いのやり方を紹介しているサイトを参考に縒ってみてもうまくいかず、なんとなくそれらしく見える編み込みっぽいようなものにまとめあげて天日干し。この時の全長は60cmぐらいで、縄状にできたのはそのうち40cmほど。
だし入り味噌だったせいかいつまで経っても微妙にしっとりしているので、変化が見られなくなった25日目で切り上げました。定点観測的に(以下略)。
両手で引っ張ってみても千切れる気配はなし。とりあえずこの時点で「いもがら縄」は完成!
そこらへんにあったものをくくってみます。
 |
 |
 |
| チップスターカマンベールチーズ味。 | コンタクトレンズ3ヶ月分(片目)。 | ウルトラの母のソフビ人形。 |
 |
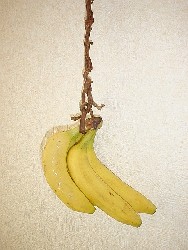 |
 |
| なぜ家に鉄粉(500g)があるのか。 | ばなーな5本。 | 未開封のラム酒(750ml)。 |
結論:いもがら縄は意外と丈夫だ。長さがないので大きい物がくくれないのが難ですが。
収集がつかなくなってきたところで、表面を濡れたキッチンペーパーで拭ったのち調理に移ります。
 |
 |
 |
| 30cm分を切り取り2cm程に刻みます。 | 拡大図。 | お椀一杯分のお湯を沸騰させて投入。 |
 |
 |
 |
| 写真を撮ろうとしても、 | あっという間にレンズが曇る…。 | 縄がほぐれてひと煮立ちしたら完成。完成? |
忍たまの友/天之巻には「きざんでお湯をそそげばインスタントの味噌汁になる」(P187)とありますが、その横の引用画像では夫丸のおじさんが陣笠を鍋にして煮ていたのでそっちに従いました。実際の戦場では、どうせお湯を沸かすなら色々な用途に使いたいでしょうから(怪我の手当てや道具の手入れとか)、鍋からお椀や柄杓に一食分だけお湯を汲んでそこに刻んだいもがらを入れて味噌汁を作ったのかもしれません。
それはさておき、5分ほど煮た後に様子を見るといもがらは柔らかくなっているものの、味噌汁らしい濁りがなくて見た目はまるで澄まし汁。
これはやっちまったかーと軽く後悔しながら火を止めます。
 |
| やっちまったかー |
では実際に食べてみます。
 |
 |
| あれ? | おや? |
……おいしい。
水で味噌を溶いたようなしょっぱいだけで味のない味噌汁(みそじる)なんだろうなー、やだなーと思いながら一口すすって、かなり本気でびっくり。
味噌の香りはあんまりしませんが、適度な塩気と出汁の旨味といもがらの風味がマッチしてます。いもがらはシャキシャキして食感が良く、ほのかに残る味噌の味がアクセントになって、味噌汁かというと違うもののような気がするけどこれはこれでおいしい。普通に食卓の一品になりそう。時間はかかりますけどね(ここまでで既に製作開始から3ヶ月経ってます)。
室町時代には無さそうな、仕方なく使っただし入り味噌が奏功したのと、当時の味噌はもっとクセと塩気が強い(いわゆる田舎味噌)んじゃないかという気はしますが、
結論:いもがら縄の味噌汁は澄まし汁になるけどおいしい。
総論
二番煎じは避けたかったので、同じような企画が実行されていないかとザッと検索してみたら、「売っている乾燥いもがらを味噌で煮て縄を作った」方はいてもいもがらを干すところからやった人はおらず、勇んで取り組んだこの企画。
世に「やってみた」サイトは多数あれど、そこそこ知名度があって簡単に作れそうないもがら縄に挑戦してみた人が何故いないのか分かりました。
手間はかからないけど時間がかかりすぎる。
そして手軽に食べられる乾燥いもがらが普通に市販されてる。
大多数の世間の人はそんなに物好きじゃない。
真面目に遊ぶのも大事だと思います と負け惜しみ。
ここまでお付き合い頂きありがとうございました!
 |
| キノコ汁食べたかー(マイタケとウスタケをプラス) |
「由無し言」へ戻る